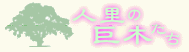 |
|
|
|||||
 |
名称 道祖神の桜 (どうそじんのさくら) 名称の典拠 現地の案内板(注1) 樹種 イヌザクラ 樹高 28m(注2) 目通り幹囲 5.2m(注3) 推定樹齢 伝350年(注2) 所在地の地名 長野県諏訪郡原村八ツ手(やつで) 〃 3次メッシュコード 5338−71−68 〃 緯度・経度 北緯35度58分23.6秒 東経138度13分28.4秒 原村指定天然記念物(1970年4月1日指定) 撮影年月日 2024年6月5日 注2)環境庁「日本の巨樹・巨木林 甲信越・北陸版」による 注3)高地側地表面から1.3mの高さで実測 八ヶ岳(やつがたけ)は、北端の蓼科山(たてしなやま、2531m)から南端の編笠山(あみがさやま、2524m)まで、南北に20km近く連なる山群の総称で、最高峰は赤岳(あかだけ、2899m)。全体として周囲から独立しているので、○○山脈と呼んでもよさそうに思うのだが、長さが足りないと考えられたのだろうか? 赤岳の1kmほど西に並び聳える阿弥陀岳(あみだだけ、2805m)から長い稜線が西に延びていて、標高が下がり、斜面の勾配が緩くなって高原をなすようになると、そこかしこに別荘地が見られる。原村の施設「八ヶ岳自然文化園」もそんな場所。 もっと西、傾斜がさらに緩くなると、裾野は水田化され、斜面を並走するいくつかの川沿いに古い集落が作られた。前沢川右岸の八ツ手集落もその一つ。 集落の中ほど、道路沿いに階段を付けた土盛りがあって、そこに様々な石造物が集められている。かつての八ツ手村と歴史を共に歩んできた物たちなのだろう。 中央にある石碑には「天照皇太神宮」と刻まれている。他には成田山、湯殿三山など、神も仏も修験も入り交じっている。お蚕さんや金山彦はこの地における生業と関わりがあったものか。甲子塔や筆塚、出征軍馬碑もある。 左図のイヌザクラが立つのは双体道祖神の後ろ。そんなことから標記のように名付けられたのだろうか?(道路や家々との位置関係から想像すると、道祖神はもとからここにあったのではなく,、近くのどこかからここに移されたのではないかと思うのだが…) それはともかく、予想していたよりもずっと大きなイヌザクラだった。樹勢も良さそうだ。 日本一の大きさを誇った大塩のイヌザクラが倒れた今、私が知る限りでは、この「道祖神の桜」が長野県随一のイヌザクラである。 |
||||