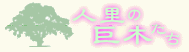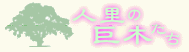|
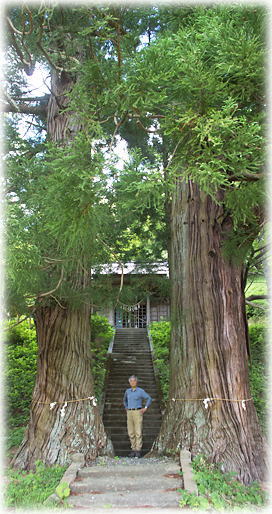 |
|
名称 塚沢八雲神社の二本杉
(つかざわやくもじんじゃのにほんすぎ)
名称の典拠 天然記念物指定名称(注1)
樹種 スギ
樹高 40m/38m(注2)
目通り幹囲 5.9m/4.7m(注3)
推定樹齢 500〜600年(注2)
所在地の地名 宮城県気仙沼市塚沢
〃 3次メッシュコード 5841−34−31
〃 緯度・経度 北緯38度56分46.5秒
東経141度31分15.9秒
気仙沼市指定天然記念物(1990年12月26日指定)
撮影年月日 2024年6月11日
注1)宮城県神社庁のサイトは「やぐもじんじゃ」の読みを示しているが、ここでは気仙沼市公式サイトの文化財紹介ページが示す「やくもじんじゃ」の読みに従った
注2)1995年3月31日に気仙沼市教育委員会が設置した案内板による
注3)私が立つ地点から1.3m上方で幹囲を実測。
(樹高・幹囲とも前者が向かって右、後者が向かって左のスギのデータ)
支流の八瀬川(やっせがわ)が本流の大川に合流する地点から、市道を八瀬川沿いに遡る。
市道が国道284号バイパスの下を2度目に潜ってから道なりに約4.5km。対岸(右側)山裾に、背が高い二本杉と赤い鳥居が見えてくる。それが塚沢の八雲神社だ。
宮城県神社庁の神社紹介ウェブページによると、創建は万寿2年(1025)。疫病退散のために勧請されたという。
とすれば、勧請されたのは牛頭天王であろう。かつては(牛頭)天王社または祇園社と呼ばれていたのではないかと想像する(拝殿には今も「牛頭天王」の扁額が掛かる)。
明治の神仏分離により、全国各地で、祇園精舎を守護する牛頭天王は神社にそぐわないと廃され、スサノオを祭神とする神社に転身した。ここもそうだったのだろう。(全国的には八坂神社になった例が多いが、宮城県では多くが八雲神社となったようだ)
八雲神社が辿った歴史はともかく、参道途中、両脇に聳える一対のスギが、今や神社の「顔」である。
いずれも神木とされ、多分、同時期に植えられたと思うが、樹皮模様が異なる等、両者の親は異なる可能性が高いように思われる。大きさについても、今は少し差が出てきた。
太さは未だ物足りない気もするが、これだけのスギが2本並び立つ姿は、単木からは得られないインパクトがある。
2本とも元気に長生きして欲しいと願う。 |
|