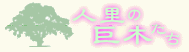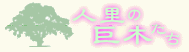|
 |
|
名称 登米神社の桂 (とよまじんじゃのかつら)
名称の典拠 なし(注1)
樹種 カツラ
樹高 25m(注2)
目通り幹囲 7.3m(注2)
推定樹齢 300年(注2)
所在地の地名 宮城県登米市(とめし)登米町(とよままち)寺池字道場(どうば)
〃 3次メッシュコード 5741-72-72
〃 緯度・経度 北緯38度39分00.5秒
東経141度16分43.6秒
登米市指定天然記念物(1976年5月21日指定)
撮影年月日 2024年6月10日
注1)それまでの八幡宮を改め、登米神社となったのは天然記念物指定時よりかなり前なのだが、何故か天然記念物指定名称は「八幡神社の桂」である
注2)宮城県公式ウェブサイト中の「登米市内の巨樹古木」による
北上川右岸、合併前の登米町中心部の南側、高台に登米神社が鎮座する。
案内板によると、登米神社は康平5年(1062)源八幡太郎義家が辺室山(へむろやま)に石清水八幡宮の分霊を勧請したことに始まる。その地は義家の父頼家が安倍氏討伐に赴いた際、鏃(やじり)を神体として戦勝を祈願した場所であった(現在、その地は八幡﨑と呼ばれる)。のち伊達氏の時代になって、慶長11年(1606)に寺池道場山麓に遷り、さらに享保7年(1722)、山上の現在地に遷座した。旧社格は県社。
社殿まで急な階段が一直線に続いていて、これが表(主)参道。他に、足腰が弱った者のためと思われる脇参道が向かって右に少し離れてつけられており、今はこちらを利用する人が多いのではないだろうか。もっとも、さらに右に進むと、車で入れる車道参道もある。
私は神社手前の駐車場に車を置き、表参道を登った。後期高齢者と呼ばれる年齢になったが、ありがたいことに、これくらいの階段なら途中で休まなくとも登れる。まずは参詣。
帰路は脇参道を下る。
カツラが立つのは脇参道入口。
生長した古い蘖(ひこばえ)を取り込んだ融合木だが、主幹がしっかり残る第一世代のカツラである。斜面に踏ん張る根が力強い。
神木とされ、立派な注連縄を付けている。
登米伊達家初代当主伊達宗直(だてむねなお、1577~1629)が八幡宮をこの地に遷した際、植えたと伝えられているようだ。(上記「登米市内の巨樹古木」による)
本当に藩主が手植えしたのなら、社殿のすぐ手前か、少なくとも表参道の近くにあるはずである。伝承については疑問を抱かざるを得ないが、余計なことは言うまい。
初代藩主を引き合いに出すほど大切にされているということで納得すべきなのである。 |
|