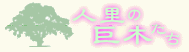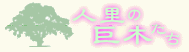|
 |
|
名称 末の松山のクロマツ
(すえのまつやまのくろまつ)
名称の典拠 なし
樹種 クロマツ
樹高 24m(注1)
目通り幹囲 3.5m(注1)
推定樹齢 480年(注2)
所在地の地名 宮城県多賀城市八幡
〃 3次メッシュコード
〃 緯度・経度 北緯38度17分15.9秒
東経141度00分12.3秒
天然記念物指定 なし(注3)
撮影年月日 2024年6月10日
注1)環境省巨樹データベース(2000年フォローアップ調査)による
注2)多賀城市保存樹標識の記述より
注3)天然記念物ではないが、国指定名勝「おくのほそ道の風景地」(2014年10月6日指定)に「末の松山」が含まれている。国名勝の一部としてクロマツも文化財保護を受けていると考えてよさそうだ
「末の松山」を訪ねた。
「契(ちぎ)りきな かたみに袖をしぼりつつ 末の松山 波越さじとは」。小倉百人一首のなかの清原元輔(きよはらのもとすけ、908〜990年)の歌である。
現代語訳は「約束しましたよね。お互いに涙でぬれた袖をしぼりながら、あの「末の松山」を波が越えないように、決して心変わりはしまいと」。(全日本かるた協会ウェブサイトによる)
この歌には下地となる別の歌があって、古今和歌集巻二十 東歌の、「君をおきて あだし心をわが持たば 末の松山 波も越えなむ」がそれ。つまり、恋する相手を裏切るようなことになれば、末の松山を波が越えるであろう、というのである。(Wikipediaを参考)
昔から知られる歌枕の地で、松尾芭蕉も奥の細道紀行の途次、ここに立ち寄っている。
かつては「末の松山」のすぐ近くまで海が迫っていたらしいが、芭蕉が訪ねたころは、もう海からは離れていたようだ。今では海岸から1.5kmほど離れた住宅密集地である。(JR多賀城(たがじょう)駅の南西約500m)
私の目的は、昔の歌に思いを馳せるのでなく、現実に存在する生きたマツ。
「末の松山」の標高は10mほど。山と呼ぶにはおこがましいほどの小さな山だ。もともとマツが数多く立っていたわけではなかろうが、今はちょっと寂しい。
道路から見上げると2本のクロマツが目立つ。そのうち右手に立つのが標記のマツである。
480年の推定樹齢が正しければ、芭蕉が訪ねた時にはもうここに立っていたことになる。(当時の樹齢は150年ほど)
芭蕉はどんな思いで眺めたのだろうか。 |
|