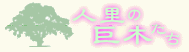 |
|
|
|||||
 |
名称 宗恵寺のイチョウ (そうえいじのいちょう) 名称の典拠 「登米市内の巨樹古木」(注1) 樹種 イチョウ 樹高 12m(注2) 目通り幹囲 5.0m(注3) 推定樹齢 伝180~200年(注4) 所在地の地名 宮城県登米市南方町尼池(みなかたまちあまいけ) 〃 3次メッシュコード 5741-70-89 〃 緯度・経度 北緯38度39分34.1秒 東経141度07分03.9秒 天然記念物指定 なし 撮影年月日 2024年6月11日 注2)「登米市内の巨樹古木」による 注3)同上。ただし同サイトで「胸高直径1.6m」とあったのを円周率倍して幹囲とした 注4)弘化年間(1844~1848)に植栽されたと伝えられている 登米市西部、JR東北本線瀬峰(せみね)駅の東約4km。西郷(にしごう)小学校からは北西200mほどの位置に曹洞宗日秋山宗恵寺がある。 宗恵寺公式サイトを拝見すると、宗恵寺の歴史のすべてが順風満帆という訳ではなかったようだが、今は境内がよく整えられ、伽藍や墓地も充実しているところから、ご住職や檀家の方々が力を合わせて寺を盛り上げてこられたことがわかる。 本堂の手前、向かって右に雌株の大イチョウが立つ。 現在、ほぼすべての木造建築物の屋根は瓦や金属板で葺かれているが、昔は藁や萱、木の皮や板などの可燃物で葺かれていた。火事が起きると大火になることが多かったのは、火の粉が拡散して起きる飛び火があったからである。従って、飛んで来る火の粉を食い止めることは防火の重要な一手段であった。 イチョウは背が高く、樹冠も大きい上に、水分が多くて燃えにくい葉を大量につける。火の粉を防ぐ防火壁として大いに役立ったと思われる。寺社で建物の近くにイチョウが植えられたのはそのためだ、という話を聞いたことがある。宗恵寺でもそうだったのだろうか。 時代が変わって、防火壁の役目を失ってみると、便利だったイチョウの葉の性質が逆に嫌われるようになった。 秋には美しく色づくイチョウだが、眺めるのはともかく、その後の処理が大変。カラカラに乾くまでに時間がかかり、なかなか落葉焚きも出来ず、ただ集めて積み上げるほかないからである。巨木ともなれば、落葉の量も半端ではない。 そのため、最近はサイズを切り詰める強剪定を受けることが多くなった。(イチョウはかなりの強剪定に耐えることが出来る) 宗恵寺では枝の落下事故を防ぐための処置だったようだが、剪定後もご覧のように葉を満載している。 いずれ、この若い枝が伸びて、新しい樹形に生まれ変わった立派な姿を見せてくれることだろう。 |
||||