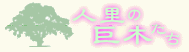 |
|
|
|||||
 |
名称 庄内柿の原木 (しょうないがきのげんぼく) 名称の典拠 天然記念物指定名称 樹種 カキノキ 樹高 5m未満?(注1) 目通り幹囲 1.5m?(注1) 推定樹齢 140年(注2) 所在地の地名 山形県鶴岡市鳥居町 〃 3次メッシュコード 5839−06−67 〃 緯度・経度 北緯38度43分39.5秒 東経139度50分18.8秒 鶴岡市指定天然記念物(1974年5月31日指定) 撮影年月日 2024年8月19日 注2)「おいしい山形推進機構事務局」のウェブサイトに、『明治18年、鶴岡市の鈴木重光氏が、新潟の行商人から数種の苗木を購入して植えた』とあることから 鶴岡市街地東部、鶴ヶ岡城趾からは東に約1.2km、JR鶴岡駅からは南(やや東寄り)に約1.4kmの住宅密集地の一角に立つ柿の木。 上記データでお分かりのように、決して巨木ではない。古木・名木というのもちょっと違う。要するに一種の産業遺産、歴史的記念樹なのである。 庄内柿は「平核無(ひらたねなし)」という品種のご当地商品名で、名前の通り、平たい形をしていて、種が無い渋柿である。(ちなみに、平核無の元祖であるわが新潟県では八珍柿(はっちんがき)と呼び、商品名は「おけさ柿」) 余談になるが、私が子供の頃は「ごま」の入った甘柿が好まれたものだ。渋柿は熱を加えれば甘くなるが、その代わり、ぐじゃぐじゃして新鮮な感じがしなくなるからである。焼酎さわし(さわす=渋を抜く)の場合は食感の変化が少なかったが、やはり少し柔らかくなった。とは言え、一度に大量に採れる柿を処理しなければならないので、大半は皮をむいて軒下に吊し、干し柿にしたものである。これには保存食の「おやつ」としての意味もあった。 完熟するまで放置しておいても甘くなるのだが、実態は薄皮を被った半液体のようなもので、とても食べにくい。 実を言うと私はこれが大好きで、逆さまにして皿に乗せ、蔕(へた)の部分を取り除いて穴を開ける。そこからスプーンを突っ込んで掬って食べるのだが、冬に炬燵で食べるときなど、甘く、冷たく、絶品である。しかし妻はこれが苦手で、かたい方が好きらしい。 その後、渋抜きの技術も進化し、今では店頭に並ぶほとんどの渋柿は二酸化炭素処理されていて、質感の変化も無く、新鮮なままである。妻は昔の甘柿よりも美味しいと言う。 閑話休題。 庄内柿の原木とされるカキノキは、古い街並みの路地の奥にある。 ある時に樹高が切り詰められたようで、少し離れると姿が見えないので、やみくもに探しても見つけるのは難しいことだろう。 鳥居町の南縁を象るように内川が流れ、その左岸沿いの道の一部が広くなっている。短時間ならば駐車可能のようだ。その近くに案内表示があるので、それを探すのが一番の近道だと思われる。 |
||||