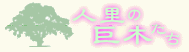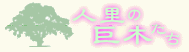|


次郎杉 |
|
名称 箟峯寺のスギ (こんぽうじのすぎ)
名称の典拠 なし
樹種 スギ
樹高 30m(注1)
目通り幹囲 5.2m(注1)
推定樹齢 900年(注1)
所在地の地名 宮城県遠田郡涌谷町箟岳(ののだけ)字神楽岡
〃 3次メッシュコード 5741-61-74
〃 緯度・経度 北緯38度33分56.6秒
東経141度10分44.2秒(注2)
涌谷町指定天然記念物(1985年7月1日指定)(注3)
撮影年月日 2024年6月10日
注1)現地の樹名板による(これは現時点で最大のスギである「三郎杉」のデータ)
注2)データの記録はしたのだが、この位置は次郎杉だったか、夫婦杉だったか忘れてしまった
注3)天然記念物としては、境内のスギ4点をそれぞれ単独で「箟峯寺夫婦杉」「箟峯寺次郎杉」等の名称をつけて指定している。なお、最大であった太郎杉もかつては天然記念物指定を受けていたが、枯死したため指定解除された
JR気仙沼線「のの岳」駅から西北西に4km強、箟岳山(ののだけやま、236m)の山頂に、奥州33観音第9番札所天台宗無夷山箟峯寺がある。通称は箟岳観音。
昔は麓から歩いて登る以外になかったが、今は自動車で行ける。(駐車場あり)
案内板によると、箟岳山は奈良時代に国内最初の金が産出した場所らしい。大同2年(807)に、征夷大将軍坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)が蝦夷征伐の後、敵味方の戦死者を弔って京都清水寺から十一面観音を勧請、法相宗霧岳山正福寺を開創。開山僧は延鎮(えんじん)。その後、嘉祥2年(849)、円仁(えんにん)が堂宇をさらに建立して天台宗に改宗、現山寺号とした。武家の時代も領主の保護を得て、ずっと栄えてきたようだ。
本堂(観音堂)の背後、山頂部分は平坦になっていて、そこにスギ巨木が散在する。
固有名のついたスギは6本。そのうち2本は根元がくっついているので「夫婦杉」と名付けられ、その他の4本は「太郎」から「四郎」まで人名のような名前をもらった。(最大のスギだった太郎杉はもう死んでしまったが、幹の途中までまだ残っている)
「寛文の鐘」の近くのスギがこれに次ぎ、まだ名前は無いが、これがいわば「五郎杉」だろうか。
なお、山頂には「おくのほそ道」展望台も設けられていて、設置当初は雄大な景色が眺められたと思うのだが、生長した木々が視界を狭めてしまっているのが残念である。 |
|