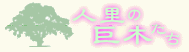 |
|
|
|||||
 |
名称 帚木 (ははきぎ) 名称の典拠 「園原の里」リーフレット(注1) 樹種 ヒノキ 樹高 − 目通り幹囲 − 推定樹齢 − 所在地の地名 長野県下伊那郡阿智村智里(ちさと) 〃 3次メッシュコード 5337−15−52 〃 緯度・経度 北緯35度27分45秒 東経137度39分18秒 天然記念物指定 なし 撮影年月日 2025年4月17日 駒つなぎの桜を見た後、リーフレットに載っていた帚木を訪ねた。 初めに帚木の名前について説明しよう。 「帚」とは掃除に使う「ほうき」のこと。 ホウキグサ(コキア)の形をした巨木が、遠くからは見えるのに、近づくとどこにあるかわからなくなる。そんな木を「帚木」と称したらしく、「人の心のうつろいや迷い・不確かなもの」の例えとされたようだ。 新古今和歌集に、三十六歌仙の一人である平安時代の貴族坂上是則(さかのうえのこれのり)の歌「園原やふせ屋におふる帚木のありとは見えてあはぬ君かな」があるらしい。 この歌に触発されたか、紫式部の源氏物語に「帚木」の帖があり、光源氏(ひかるげんじ)と空蝉(うつせみ)がそれぞれ「帚木の心を知らで園原の道にあやなく惑ひぬるかな」(光源氏)、「数ならぬ伏屋(ふせや)に生(お)ふる名のうさにあるにもあらず消ゆる帚木」(空蝉)と歌っているそうだ。(以上、上記リーフレットを参考) 駒つなぎの桜から道なりにさらに800mほど登って行くと、帚木見学者と暮白(くれしろ)の滝見学者のための駐車場があり、そこから山道を約5分。稜線上に帚木が立っていた。と言っても、今は骸になってしまったが。 リーフレットによると、根回り6m、高さ22mほどあったが、大正時代初期に2幹のうちの1本が倒れ、昭和33年(1958)の台風で残る1本も倒れた。今は左図のような姿である。地上1.3mの幹回りは、目分量で4.5mほどだろうか。(背後に見える幹は、帚木とは別のヒノキ) 平安時代に既に大木であった帚木がこれだとは信じがたい。とうの昔に失われた帚木の面影をこの個体に求めたというのが真相ではないだろうか。 その新「帚木」も、今では遠くからも見えなくなってしまった。 |
||||