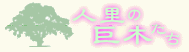 |
|
|
|||||
 |
名称 国庁裏神社のスダジイ (こくちょうりじんじゃのすだじい) 名称の典拠 「今日もおでかけ」ブログ 樹種 スダジイ 樹高 21m(注1) 目通り幹囲 6.3m(注1) 推定樹齢 なし 所在地の地名 鳥取県倉吉市国分寺 〃 3次メッシュコード 5333−16−13 〃 緯度・経度 北緯35度25分53.6秒 東経133度47分10.6秒 天然記念物指定 なし 撮影年月日 2024年9月5日 倉吉市街地の西方、国府川(こうがわ)左岸の高台に、かつて伯耆国の国府があった。発掘調査によって遺跡が見つかり、国庁や国分寺等いくつかの重要施設の位置も確定されて国指定史跡となっている。 その一つ「伯耆国府跡 国庁跡」史跡のすぐ東に国庁裏神社が鎮座する。(神社本庁への登録名は國廳裏神社だが、通例に倣い新字で表記させていただく) 鳥取県神社庁の神社紹介ウェブページの内容を要約すると、伯耆国々造(くにのみやつこ)に任命された大八木足尼(おおやきのすくね)が国庁を設置した際に、大国主命(おおくにぬしのみこと)と少名毘古那命(すくなびこなのみこと)を国庁の中に祀って国庁裏神社と称したことが始まり。 その後、元明天皇2年(709、和銅2年)、国司金上元為が伯耆国中の神社を集め、総社として祭典を行った。それゆえ、近世に至るまで総社あるいは伯耆国総社大明神と称された。明治初年(1868)、国庁裏神社と改称。最終的な旧社格は県社。 なかなか立派な社叢があって、その全体が「伯耆国府の森」の名称で倉吉市から保存林指定を受けている。 モミとトガ(ツガ)が目立つなか、群を抜いて大きいのが左図のシイの木。拝殿と本殿の間、向かって左側。樹林の周縁部に立つ。 発達した板根のため、地表に近づくにつれ急激に幹囲を増しているため、実感よりも大きいデータとなっているが、板根の眺めはなかなか見事。 樹姿にも威厳が出て来たように思われる。 |
||||